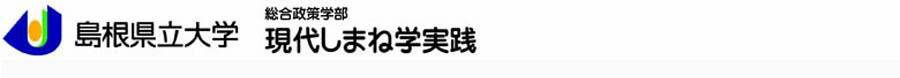
������
���h���C�\�\�܂Ƃ߂̃��[�N�V���b�v
 �@���h���C�̍ŏI���ɂ́A�l�c�s��h�x����1��c���ɂ����āA�܂Ƃ߂̃��[�N�V���b�v���s���܂����B
�@���h���C�̍ŏI���ɂ́A�l�c�s��h�x����1��c���ɂ����āA�܂Ƃ߂̃��[�N�V���b�v���s���܂����B
�@�܂��A��u��10����5�����̃O���[�v�ɕ�����A���ꂼ��A���̂��т̍��h���C���ЂƂ̔_���̌��v���O�����ƂƂ炦�A���̗ǂ������_�Ɖۑ肾�Ǝv��ꂽ�_��o���܂����B������ӂ܂��āA�_�ƁE�_�����h���̂��Ƃ��Ⴂ�l�X�ɓ`���邽�߂̑̌����痷�s�̃v���O�������l���Ă݂܂����B���ʂ́A���ꂼ��̃O���[�v���甭�\���Ă��炢�A�S�̂ŋ��L���܂����B
�@�������Ȃ���A��Ă��ꂽ�v���O�����́A�܂��܂��u���b�V���A�b�v����K�v����������ꂽ���߁A�A�w��ɂ������c�_��[�߂邱�ƂƂ��܂����B����܂Ƃ߂�ꂽ��u���̍�i�����������������ł��B�@
���h���C
 �@9��15��(�y)�`17��(���E�j)�ɁA�l�c�s��h���ɂ����āA���h���C�����{���܂����B1���ڂ́A�����g�������̌��A�_�ƁE�_���u�b�A�Ԕ��̌��ƃn�[�x�X�^�Ȃǂ��g������Ƃ̌��w���A2���ڂ́A���y�������K�A�k������n�Đ��̎�g���w�Ƒ�����̌����A3���ڂ́A��̎��n�E������Ƒ̌��A�ĕ��s�U�Â���Ɛ��Ď{�݂Ȃǂ̌��w�A�܂Ƃ߂̃��[�N�V���b�v���s���܂����B
�@9��15��(�y)�`17��(���E�j)�ɁA�l�c�s��h���ɂ����āA���h���C�����{���܂����B1���ڂ́A�����g�������̌��A�_�ƁE�_���u�b�A�Ԕ��̌��ƃn�[�x�X�^�Ȃǂ��g������Ƃ̌��w���A2���ڂ́A���y�������K�A�k������n�Đ��̎�g���w�Ƒ�����̌����A3���ڂ́A��̎��n�E������Ƒ̌��A�ĕ��s�U�Â���Ɛ��Ď{�݂Ȃǂ̌��w�A�܂Ƃ߂̃��[�N�V���b�v���s���܂����B
�@�ĂƂ�����Ƃ�܂�����،��ɁA��h����_�ƁE�_���̌�����w�сA���R�Ԓn��̔_�n�̑����͌��Ɣ_�Ƃɂ���Ď���Ă��邱�ƁA�_�Ə]���҂�������Ă��邱�ƂȂǂ�m�邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�_�ƁE�_���̉ۑ���������Ă����ЂƂ̎����Ƃ��āA�s�s�Z�������҂Ƃ̌𗬂�A�g�ɂ��čl���܂����B
���h���C�\�\��u���̃��|�[�g

���̌�
�@���h���C�̍ŏ��̊����Ƃ��Ĉ��̌����s���܂����B�O���̉J�̂��ߕޏ�͂ʂ���ł���A�������Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��ł����B������Ŋ����ƁA�Ђ��Ō���ň�������ƁA����^�сA��˂Ɋ|�����Ƃ�����܂������A�u�n���ē��l�v���V�����Ă��˂��Ɏw�����Ă��������܂����B�������ŁA�D���炯�ɂȂ�Ȃ�����A�����ɍ�Ƃ�i�߂邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B��1����30���̍�Ƃł����B�����˂Ɋ|���邻�̕��@�ɂ����ӂ������邱�ƂȂǁA���낢��Ɗw�Ԃ��Ƃ�����܂����B�n���̔_�Ƃ̕����ӂ��͂��Ȃ��悤�ȁu�������v�́A�������ɂƂ��Ă��y�����A�M�d�Ȍo���ƂȂ�܂����B�kYK�l
 �_�ƁE�_���u�b
�_�ƁE�_���u�b
�@�l�c�s��h�x���Y�Ɖۂ̉������l����ɁA�u���Ă��猩���Ă���_�ƁE�_���̂��b�v�Ƃ�������ōu�b�����Ă��������܂����B�Ⴆ�A�_���͌��Ɣ_�Ƃɂ���Ď���Ă������ƁA�ĉ����������Ă��邱�ƁA�_���Ɠs�s���������Ă������߂ɂł��邱�ƂȂǁA��u�����m��Ȃ��������Ƃ����Ȃ��Ȃ������ł��B
�@���̌�A��������Ǝ�u���Ƃňӌ��������܂����B�����Řb��ɂ��������̂́A�_�ƂƔ_������邽�߂ɂ��Ă�H�ׂĂ��炢�����Ƃ����b�ɑ��āA����ł́A�ǂ������炨�Ă�H�ׂĂ��炦��̂��Ƃ������Ƃł����B
�@���̍u�b�̂������ŁA�������̗������[�܂����Ǝv���܂��B�kMI�l

�}���s���̐X���@�E�Ԕ��̌�
�@�Ή��X�ёg���Ɩ�h�x���Y�Ɖۂ̂��ē��ŁA�}���s���̐X�ɂ����āA��i�I�ȃn�[�x�X�^���̋@�B��p������Ƃ̂悤�������w���A�Ԕ��̍�Ƃ�̌����܂����B�}���s���̐X�́A��h���O���E��c�ɂ���ʐϖ�500ha�ɂ���Ԏs�L�тŁA���̂�����340ha���q�m�L����̂Ƃ���l�H�тƂȂ��Ă��܂��B
�@�ŋ߂̗ыƂ͋@�B�����i�݁A�قڋ@�B�����ŊԔ���Ƃ��s����ɂ���悤�ł����A�Ԕ��̌��́A�̂�������g���Ď��Ƃōs���܂����B3�l1�ǂɂȂ��āA���ꂼ��1�{�̖点�Ă��炢�܂����B�Ԕ��͂Ȃ��Ȃ��o�����邱�Ƃ��ł��܂��A��Ƃ̂����ւ�g�������Ė��킢�A�ƂĂ��M�d�ȑ̌��ƂȂ�܂����B�kYM�l
 ���y�������K
���y�������K
�@���y�������K�ł́A�l�c�s�H�������P���i���c���h�x���݂̂Ȃ���̎w���̂��ƁA���Ẵn���̓��̗����A�u�₳���̂��Ղ�V�v�ɒ��킵�܂����B�����́A�p���i�A�������i�A���Ȃ���i�A���荞�݁A�ϕ��A�|�̕��A�a�����A�V�Ղ�A�`���A�ϋ��A�h�g��11�i�ł����B�ŏ��͊���Ȃ���ƂɂƂ܂ǂ�������܂������A�Ă��˂��Ɏw�����Ă��������A�ЂƂЂƂ��Ȃ��Ă������Ƃ��ł��܂����B
�@���H�𗬉�ł́A��h�̐̂̕�炵��H�����ɂ��Ă̂��b�����������Ȃ���A�ł��������������������������������܂����B����̎��K�ŋ����Ă������������Ƃ��A���������̂��ꂩ��̐����Ɋ������Ă��������Ǝv���܂��B�kOY�l

�k������n�Đ��̎�g���@�E������̌�
�@�k������n�Đ���Ȃǂ̕⏕�������p���ăr�j���n�E�X�����݂��ꂽ��g�����@���܂����B���̌o���k���A�����ւ�ȋ�J�̌��ʂƂ��āA��h���̔_�Ƃ��x�����Ă���̂��Ǝv���܂����B�n�E�X�����J�̏㗬�����l�ɂ��Ă͓c�ł������ƕ����܂������A�����A���Ă̂悤���͑z��������̂ł����B�킸��1�N�ł��ێ��Ǘ���ӂ�ƁA�c�����r��ʂĂ邱�Ƃɂ͋����܂����B�kRM�l
�@�܂��A���ۂɗV�x�_�n�̑������̌����܂����B��r�I�ŋ߂܂ō�t������Ă����ޏꂾ�ƕ����܂������A���܂�̎G���̑����ɁA�݂Ȉ���ꓬ���A�c���Ɣ������i�ς�����Ă������Ƃ͂����ւ������Ƃ��Ǝ������܂����B�kKY�l
 ��؎��n�E�����̌�
��؎��n�E�����̌�
�@�͂��߂ɁA�s�[�}���̎��n��Ƃ����܂����B�n�T�~�Ő�l�Ƃ��������l��2�l1�g�ɂȂ��Ă̍�Ƃł����B���ɁA�r�j���n�E�X�����w�����Ă��炢�Ȃ���A�͔|���Ă�����g���Ă���엿�̂��b���܂����B�����b�ɂȂ��������t�@�[������́A�L�@�_�ƂɎ��g��ł����܂��B�엿�Ɏg���ݖ��̍�肩���������Ă��炢�܂����B���̌�A�s�[�}���̒�����Ƃ�̌����܂����B�������́A�s�[�}���̑I�ʁA�v�ʁA�܂Â߂̍�Ƃ������Ă��炢�܂����B
�@���J���悤�̂����ɂ��̓V��ł������A�ƂĂ��M�d�Ȍo���������Ă������Ǝv���܂��B���Y���Ă�����X�̂��ӂ���z�����āA��������Ƃ������ɐH�ׂ悤�Ǝv���܂����B�kNK�l

�ĕ��s�U�Â���
�@�ق��̑̌��𗬎{�݂ŁA�ĕ��s�U�Â���A���т̊������̌��������Ă��������A�܂��A���čH������w�����Ă��������܂����B
�@�ĕ��s�U�́A�ĕ��ƃh���C�C�[�X�g�Ɖ��Ɛ��Ȃǂ������A���˂Đ��n������A���炭�u������A���n��L���ăg�b�s���O�����A���ŏĂ������܂����B�ł����ĕ��s�U�́A�������ł���s�U�ƌ����ڂ□�͕ς��Ȃ����̂́A�����e�͂�����H�������`���`���Ă���悤�Ɏv���܂����B
�@���Ă̐���A���ł̂��т̐��������K���܂����B�ߔN�A�Ă̏���ʂ��������Ă���Ƃ������b�������܂������A���������A�����Ƃ��Ă�H�ׂ邽�߂̂��ӂ������������̂ł��B�kAM�l
 �h���E�[�H�̎���
�h���E�[�H�̎���
�@�������́A2�ӁA�ӂ邳�Ƒ̌����̃��O�n�E�X�ɔ��܂�܂����B���O�n�E�X�́A2010�N�����z���ꂽ�悤�ŁA�����̒��͖̍���ł����ς��ł����B���ꂾ���łȂ��A���O�n�E�X�͖ؗ��̒��Ɍ��Ă��Ă���A���R�̒��ɐQ���܂肷�銴�o�ł����B
�@�܂��A�[�т͎������܂����B�P���ڂ̓o�[�x�L���[�����A�Q���ڂ̓J���[������܂����B��������A�ӂ邳�Ƒ̌����̎{�݂𗘗p�����Ă��炢�܂����B�N�����ɋ�킵����A�H�ނ̒��B���x�ꂽ��A���т̗ʂ�����������Ƃ������n�v�j���O������܂������A�������邱�Ƃ�ʂ��āA���含�����܂�A��u���ǂ����̒����[�܂����Ǝv���܂��B�kYT�l
���O�w�K

�@8��1��(��)�ɁA���O�w�K�̂��߂ɁA�l�c�s��h����K��܂����B�l�c�s��h�x���Y�ƉۂɂĎ�������S�����������Ă��鉪�������Ή��X�ёg���̑勴�����Ɗ獇�킹���s���A��h���̊�b������������������A���h���C�Œn���ē��l�����Ă��������������⏬���������K�ˁA���C�ꏊ�������Ă��炢�܂����B���̌�A���������@�����Ă��炢�܂����B���A���p�A�����A�c�쌴�Ȃǂ̂������̏W����A���h���C���ɂ͏h�����Ƃ��Ďg�킹�Ă��������ӂ邳�Ƒ̌����A�������̓V�R�L�O���ƂȂ��Ă��钷���{���̔����{���ؐ��Ȃǂ����w���܂����B
�@��u���������A��h���͂ǂ̂悤�Ȓn��Ȃ̂��A�����܂��Ȃ��痝�����邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���O�w�K�\�\��u���̐�

�@��h�n��ɓ������Ƃ��A�܂��ڂɔ�э���ł����͔̂������i�ςł����B��̓I�ɂ́A�����납�����ꂳ��Ă���A���ʂɍL����c�����i����ۓI�ł����B��ʓI�ɂ́A���̂悤�Ȓn��ł͐l�H���͌i�ςȂ��Ƃ����l��������܂����A��h�n��̏ꍇ�́A���R�̌i�ςɍ������l�H��������A���ꂪ���R�ƍ��킳���āA�ނ���A��肢�������i�ς��������������܂����B���ɁA����_�ЂȂǂƂ��������j����������ؑ����z�����R�̒��ɂƂ�����ł���̂ł��B���̂��Ƃ���A�̂Ȃ���̌i�ς��ێ����A���R�Ƃ̋������ł��Ă���n��ł���Ǝv���܂����B�kRM�l
 �@������������h���̂悢�Ƃ���̈�ڂ́A�i�ς̔������ł��B��h���͐��c�������A��ɑ��z�̌������˂��đN�₩�ȗɂȂ�A�ƂĂ����ꂢ�ł����B
�@������������h���̂悢�Ƃ���̈�ڂ́A�i�ς̔������ł��B��h���͐��c�������A��ɑ��z�̌������˂��đN�₩�ȗɂȂ�A�ƂĂ����ꂢ�ł����B
�@�����āA��ڂ͂��̔������i�ς�������ƈێ�����Ă���Ƃ���ł��B��h���̐l���́A2012�N6�����݂�1,497�l�ƁA1960�N���s�[�N�Ɍ����X���ɂ���ƕ����܂������A���̊��ɂ́A�k������n�����Ȃ��Ɗ����܂����B�܂��A���ɂ��\���g���l�������Ƃ���ł͖̙������肪����Ă�����A�R�̒��܂œ��H�ܑ̕�������Ă�����ƁA�ׂ����Ƃ���܂Ŏ���ꂪ�s���͂��Ă���A���S�̂Ɍ}��������Ă���C���ɂȂ�܂����B�kAM�l
 �@��h�ɂ͏��߂čs���܂����B�K�ⓖ���͂ƂĂ����������ł����A���̋߂����Ɨ����������܂����B��̋߂�������Ă݂��������ł��B��̏㗬�̂ق��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤�ƋC�ɂȂ�܂����B�����ƂĂ��Y�킾�������Ƃ���ۂɎc��܂����B
�@��h�ɂ͏��߂čs���܂����B�K�ⓖ���͂ƂĂ����������ł����A���̋߂����Ɨ����������܂����B��̋߂�������Ă݂��������ł��B��̏㗬�̂ق��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤�ƋC�ɂȂ�܂����B�����ƂĂ��Y�킾�������Ƃ���ۂɎc��܂����B
�@�Y�킾�����Ƃ����A���c�̈���ɂ��߂��Ă���Ƃ�����Y��ŁA�������܂����B���ł��N���Ɏv���o����قǂł��B
�@�߂����猩�����c���Y�킾�Ɗ����܂������A�����Ƃ��납�猩�����c��R�X�̌i�F�́A�����̎v���Y��ł��邱�ƂȂ�Ăǂ��ł��悭�Ȃ�悤�ȋC�����ɂ����Ă���܂����B
�@��h�ɂ͎��R�����ӂ�Ă���A������҂�A�ӂ邳�Ƃ̖��͂������邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B�kYT�l
 �@������������h���̖��͓I�ȂƂ����2����܂��B�P�ڂ͋��y���������������Ƃ���ł��B��ł����₤���ߔтȂǂ̋��y�����͂��̒n��Ȃ�ł͂̓`���I�ȗ����ł��B�������̂��ƂĂ����N�I�ŁA���܂��A�����W���Ă������̓��{�̌��N�u�[���ɏ�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���������K�ꂽ��h�ӂ邳�Ƒ̌����́A�킩��ɂ����ꏊ�ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���K�҂ɂ킩��₷���ꏊ�Œ���Ȃǂ̂��ӂ�������A��h���̗����L���m���Ă��炤���Ƃ��ł��A���K�҂�ʂ��čL��PR�ł���̂ł͂Ȃ����ƁA���͎v���܂��B
�@������������h���̖��͓I�ȂƂ����2����܂��B�P�ڂ͋��y���������������Ƃ���ł��B��ł����₤���ߔтȂǂ̋��y�����͂��̒n��Ȃ�ł͂̓`���I�ȗ����ł��B�������̂��ƂĂ����N�I�ŁA���܂��A�����W���Ă������̓��{�̌��N�u�[���ɏ�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���������K�ꂽ��h�ӂ邳�Ƒ̌����́A�킩��ɂ����ꏊ�ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���K�҂ɂ킩��₷���ꏊ�Œ���Ȃǂ̂��ӂ�������A��h���̗����L���m���Ă��炤���Ƃ��ł��A���K�҂�ʂ��čL��PR�ł���̂ł͂Ȃ����ƁA���͎v���܂��B
�@2�ڂ͖�h���̌i�F���ƂĂ��ǂ��Ƃ���ł��B�R���Ȃǂ̖L���Ȏ��R�Ɍb�܂ꂽ��h���̌i�F�͌��Ă��邾���Ől������悤�ȗ͂�����܂��B�����A���_�Ƃ��Ď��������邱�Ƃ́A�����i�F���ǂ������ł͑��̒n��ɃA�s�[�����ɂ����A���ꂾ���Œn������������邱�Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B���́A���̒n��̖��𑽂͂��̐l�X�ɒm���Ă��炤���߂ɁA��h���ɂ����Ȃ����͂���������ꏊ�A���̏ꏊ���g���ė��K�҂ɂ����ł��炦��悤�ȃA�g���N�V�����������Ă����x�����Ǝv���܂��B���ɓ�����Ƃł͂���܂����A�n��Z����O���̐l�̍l���Ȃǂ�����������Ď������Ă����A���������h���ɕω��������炷�̂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă��܂��B�kSY�l

�@���͍���̎��O�w�K�ŁA���߂Ė�h��K��܂����B���ۂɖK�₷��܂ł͂ǂ̂悤�ȂƂ��납�S���z���ł��܂���ł������A�Ƃɂ������R�ɂ��ӂꂽ�����Ƃ������Ƃ�������܂����B�K�₵���̂́A�悭���ꂽ���������̂ŁA���R�̗Ƌ�̐����ƂĂ���ۓI�ł����B��h�̕��i������ƁA�N�����A�ǂ������������A����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@����̖K��ł́A����̌����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������Ƃ�A�C�Â��Ȃ��������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���Ǝv���̂ŁA��h�̖��́E�ۑ������ƂƂ��ɁA����̊w�тɂ��Ȃ��Ă����������̂��Ǝv���Ă��܂��B�kYO�l

�@���͍���A���߂Ė�h����K��܂����B��h�����̏W���́A�ǂ����R�Ɉ͂܂�A�c��ڂ��L�����Ă��āA�ƂĂ����R���L���ł����B��C�����ꂢ�ŁA�C�����悩�����ł��B��h���������w���Ă���ԁA�Z����ԂƂقƂ�ǂ�����Ȃ������̂ŁA�ߑa�����i��ł���̂��Ɗ����܂����B�������A������������ł́A���܂�k������n�͂���܂���ł����B���̂��Ƃ́A���ɂƂ��ė\�z�O�ŁA�����܂����B����̖K��ŁA�ق�Ƃ��ɂ��̒n���Z���������Ă���ۑ�𗝉������Ƃ͎v���Ă��܂���B������A������ʂ��Ă�����Ɨ������A��������l�������ł��B�kNK�l
�₢���킹
��697-0016
�������l�c�s�쌴��2433-2
����������w��������w��
�� �G�i������
TEL. 0855-24-2234
FAX.